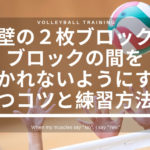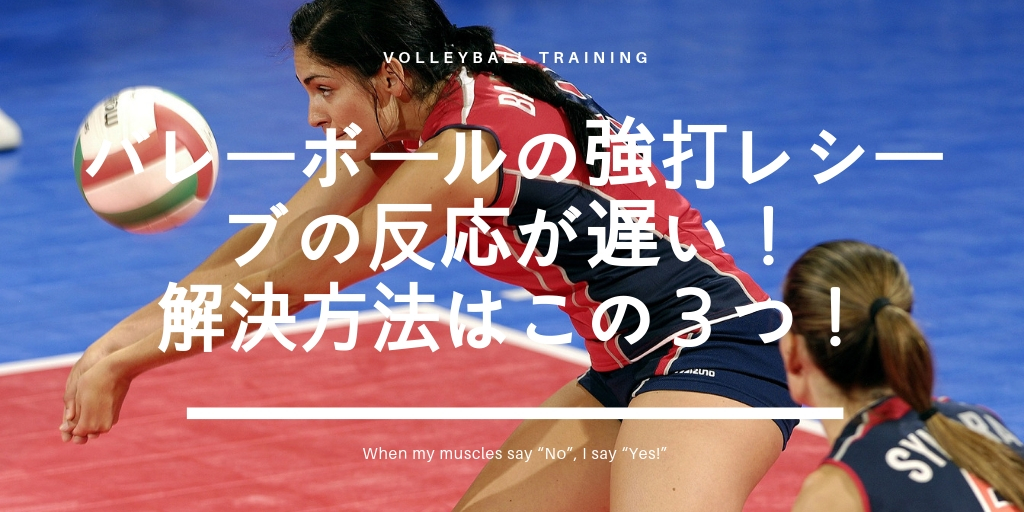
Contents
打たれる前にレシーブの準備をしておく
強打レシーブは打たれるまでにどれだけ準備できるかが重要です。スパイクは速いので打たれてから構えているようでは反応が追い付かずレシーブが上がりません。まずはいつ打たれても大丈夫なようにレシーブの準備をしておきましょう!
①腰を低く構えておく
強打レシーブをする時は、腰を低い状態にして構えておきましょう!足元に打たれたスパイクをレシーブで拾う時に、ボールが飛んで来てから構えているようでは間に合いません。打たれてから腰を上下させるのではなく、いつでもレシーブできる構えでスパイクを待ちかまえるように意識しましょう!
②腕が下がった状態にならないようにする
レシーブする腕が下がった状態では、速いスパイクに対して反応が遅れてしまうのです。反応が遅れないためには「腕にボールが当たったらレシーブが上がる状態」で構えておくことが大切です。レシーブする時にこのポイントを意識して行うことで、レシーブの反応が間に合わないというミスを防ぐことができます。
スパイクが飛んでくるコースを予測する
速いスパイクは飛んでくるコースを事前に予測しなくては拾い上げることは難しいです。スパイクが飛んでくるコースを予測するためには、3つのポイントが大切です。
- スパイクを打つ選手の助走や体勢をみて判断
- セッターのトスの位置で判断
- 打数が多い選手(エース)の得意なコースを把握
①スパイクを打つ選手の助走や体勢をみて判断
スパイカーの体勢や助走からスパイクを打ってくるコースがクロスなのか、ストレートなのか判断してみましょう。スパイカーの体勢がクロスにしか打てないような場合は、クロスを意識して拾うようにポジショニングしましょう。
ボールに被り気味でスパイクしている場合は鋭角には打ちにくいのでコート奥に打つ足の長いスパイクになる可能性が高いです。このようにスパイカーの状態を見ながら、「この体勢ならクロスにしか打てない!」「この助走だとストレートだ!」と意識して打たれる前にコースを予測するクセをつけましょう。
②セッターのトスの位置で判断
セッターのトスからもスパイクのコースを予測することができます。トスが短い場合は、助走が間に合わないのでクロスに打つことが多いですし、トスがしっかりアンテナまで伸びている場合はストレートコースが多いです。
トスがネットから離れている場合は、スパイクを鋭角には打ちにくいのでコート奥への足の長いスパイクになる可能性が高いです。セッターのトス次第でもスパイクの打てるコースは限定されるので、トスを見てスパイクが抜けてくる可能性が高いコースを予測してレシーブするようにしましょう!
③打数が多い選手(エース)の得意なコースを把握
事前に敵チームのスパイカーを研究して得意なコースやクセなどを見つけておきましょう。スパイカーは苦しい時にも調子がいい時にも得意なコースにスパイクを打つことが多いです。まずは一番打数の多いスパイカーであるエースの得意なコースを把握しましょう。
チームでどこをレシーブで守ってどこをブロックで抑えるか決めておくことで、相手のエースの決定率を落とすことができるのです。
レシーブと味方のブロックと連携する
レシーブはどれだけすごいレシーバーでもブロックがない状態では、全く拾えません。ブロックの役割はシャットアウトすることだけではありません。
- スパイクが打たれるコースを限定する
- ワンタッチを取ってスパイクの威力を弱める
ブロックにはシャットアウト以外にもこのような役割があります。ブロックでスパイクを打たれるコースを限定して、空いているコースにレシーバーを配置するようにしましょう。相手のスパイカーがストレートが得意なのであれば、ストレートにブロックを配置してレシーバーはクロスを拾うようにレシーブの位置取りを考えましょう。
そうすることで、相手スパイカーはストレートの決定率が落ちます。ストレートが決まらないので、クロスに打てばレシーバーがキッチリ準備して守っているという状態になるのです。ブロックとレシーブが連携することで、チーム全体の守備力をぐっと上げることができるのです!まずは話し合ってどのコースをブロックで閉めて、どのコースをレシーブするのか決めてやってみましょう!
まとめ
レシーブは個人の拾う能力をアップすることも大切です。その他にも「チームで連携して守備力を上げる」ことも非常に大切です。ブロックとレシーブが連携することで今まで拾えなかった強烈なスパイクも拾い上げることができるようになります。
レシーブの反応が遅れていたスパイクにも抜けてくるコースが限定されていれば、簡単に反応できるようになります!3つのレシーブの反応が遅れない方法をチームみんなで試してみてくださいね!
★その他のレシーブのコツはこちら!